インタビューシリーズ:親も子もトライ&エラー
日々、親ごさんと接しているかたや、子育て奮闘中のかたにお話を伺っていきます。
シリーズ第10回 その3
自分の意見を
言える子どもに育つには?
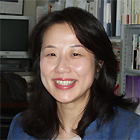
唐澤真弓さん
プロフィール
東京女子大学現代文化学部
コミュニケーション学科教授
今回のお客様は東京女子大学教授の唐澤真弓さん。それぞれの国の文化の違いが、子育てや教育にどんな影響を与えているのか、それが子どもの心の発達にどう関わるのか、国際比較を研究しています。ところ変われば、子育ての常識も変わるようです。
Part1 正しい子育ての方法はひとつではない
Part2 子育ては「答え」を自分で作っていく作業
Part3 自分の意見を言える子どもに育つには?
Part4 同じであれ、という雰囲気のなかで、自分らしさを大切にするには?
2008年2月27日掲載
編集部:文化によって育てかたがそれぞれ違うとはいえ、何か、見習ったほうがよいと思うことはありますか?
唐澤:気になるのは、日本の子どもが自分の言いたいことを、なかなか言えないことですね。自己主張する力が足りないと感じます。
その背景には、言葉に出さずに「気持ちを察する」ことでコミュニケーションをとってきた日本の社会や家庭の環境があるでしょうし、自分の意見を言う機会が少ないことも原因のひとつだと思います。
編集部:他の国では、どうですか?
唐澤:日本と同じ集団主義と言われる中国の幼稚園では、子どもに童話などのテープを覚えさせて、その内容や感想をクラスメイトの前で15分くらい発表させます。
日本では大学生でも一人15分しゃべるのは大変ですが、中国では全員の子がしゃべる。しかも、子どもにとってそれは「自分に与えられた、待ち遠しい時間」だとか。実際、いま日本にいる中国人留学生に聞くと、「自分の発言をみんなに受け入れてもらえて楽しかった」と言います。
発表後は、その発表に対してメダルをあげてもよいかどうか挙手で決める。「声が小さかった」とか「わかりやすかった」といった理由も言ってもらって、発表者はそれらの批評も受けとめていくんです。

編集部:日本でも、人前で発言の機会が増えれば、自分の意見を言えるようになりますか?
唐澤:それも大事ですが、まず、「自分の思いや考えが、他人と違っていていい」と、言ってあげることが必要だと思います。
編集部:たしかに、「個性を大切にしよう」と教室に貼ってあるけれど、実際は、人と違うことが歓迎されない囲気がありますね。
唐澤:反対に、アメリカでは「仲良くしましょう」というポスターが貼ってあったりします(笑)。「自立」や「自己主張」はすでに達成されているので、あえてスローガンとして掲げる必要がないのでしょう。
編集部:どうすれば、自分の考えを言えるようになりますか。

唐澤:アメリカでは、子どもが小さい頃から親が「好きな色は何色?」「何を飲む? アイス?ホット?」など、些細なことも本人の好みを聞きます。親も「私はこれが好き」と主張する。
意見が違ったときは、お互いにとことん主張したうえで、話し合って妥協点をみつけていきます。
一方、日本では、親が子どもの気持ちを先回りしていろいろ用意してしまう。それは良い面もありますが、もう少し子どもの意見を聞いたり、親のほうも意見を言ったりして、意識的に自己主張のトレーニングをするといいと思います。
もちろん日本にいる限り、周囲とバランスをとって浮きすぎないようにすることも大事ですが、相手の気持ちをふまえて、自己主張する力も伸ばせるといいと思います。
ミニコラム 日本の常識、海外の常識
全員、わがままな客??(アメリカ)
幼いころから自分の好みや考えを言う機会が多いからでしょうか。アメリカのスターバックスではみんな、後ろにどんな長い列ができているとき、「ミルクはローファットで」「粉を振りかけて」と好みを細かく注文しても平気でいます。後の人も誰も怒らない。
日本では、オーダーメイドすることさえ思いつかなかったりしますね。思いついても、「後ろに迷惑をかける」「わがままと思われてしまう」と気になって、なかなかできないことが多いようです。